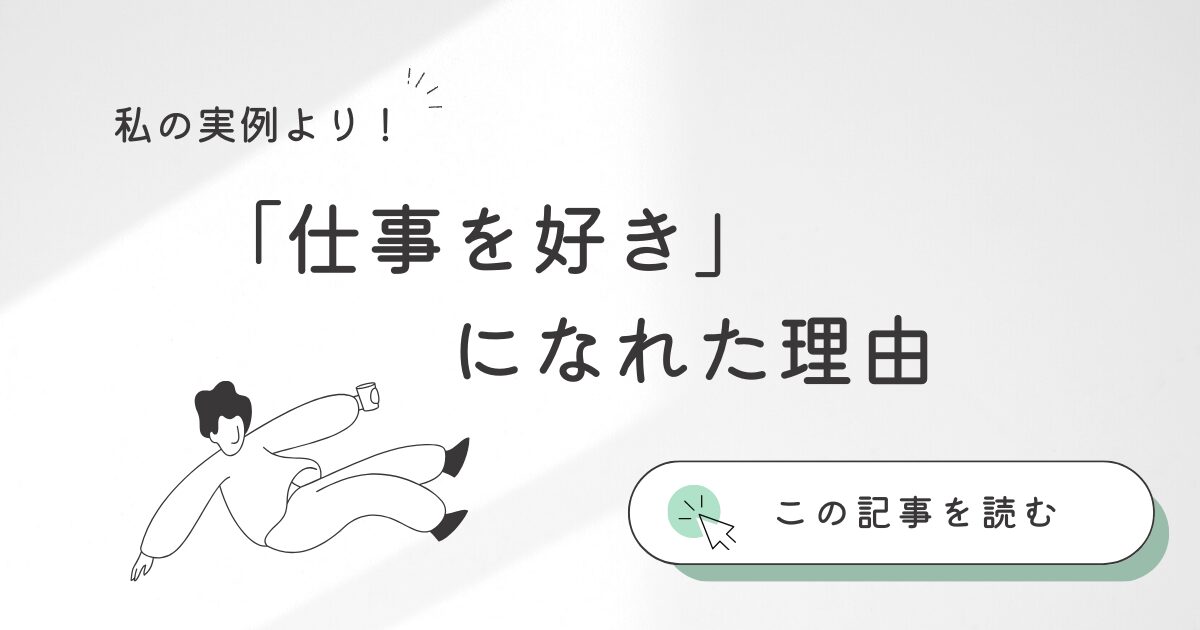「お酒をやめたいけどやめられない」人へ。酒と上手に付き合う方法

突然ですが、あなたはお酒が好きですか?
私はお酒が好きです。
特にビール。あの黄金色の液体をグラスに注ぐときの音、泡の立ち方、喉を通った瞬間の心地よさ。
一日の終わりに、あの一口を流し込む瞬間ほど「くぅーーッ!!」と思うことは、そう多くないかもしれません。
美味しいし、楽しくなる。
酔うと、少しバカになれる。
頭の中のもやもやも、肩の力も、どうでもよくなってくる。
饒舌になり、「あぁ、これでいいんだ」と思える。
それが、私にとってのお酒の“効果”です。
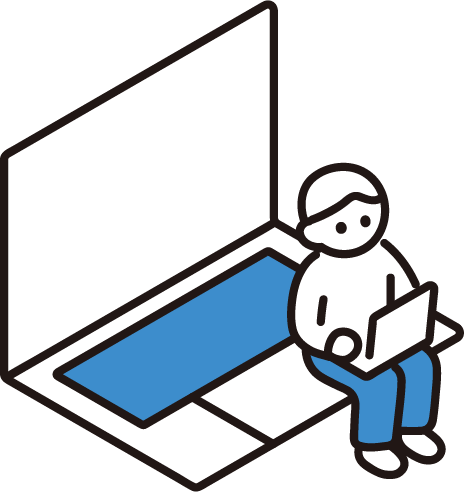
好きなビールは「一番搾り」です。
翌朝の現実
けれど、翌朝になるとその“代償”を思い知らされる。
身体は重く、頭は働かない。
鏡の前に立つと、なんとなく顔がむくんでいる。
声は枯れ、心も体もフレッシュさを失い、どこか鈍い。
そう、「愚鈍」という言葉がしっくりくる感じ。
1日だけなら、まだ軽症です。
けれど、それが2日、3日と続くと、鈍さが積み重なってくる。
やる気も、集中力も、感性も、少しずつ鈍くなっていく。
それが積もり積もって、自分自身に対し「最近なんかパフォーマンス落ちたな」と感じる。
この 静かな侵食こそが、お酒の本当の“代償” なのかもしれません。
性格まで変わってくる?
そしてもうひとつ。
少し怖いのが、性格の変化。
お酒が続くと、どこか短気になったり、思考が浅くなったりする。
理性的な自分より、感情的な自分が前に出てくる感じ。
些細なことにイラッとしたり、後から思えば「なぜあんなこと言ったんだろう」と反省したり。
ほんの少しずつの変化だからこそ、気づきにくい。
でも確実に、飲み続けると“人格のトーン”が変わってくる。
それに気づいた時、「あ、これよくないな」と思うんです。
じゃあ、やめればいいのか?
……と言っても、簡単にはいかない。
お酒を完全にゼロにするなんて、たぶん私にはできません。
というより ここ3年間、何度も断酒には成功している んです。
1ヶ月から長い時では半年くらい断酒を継続できた。
しかし、一定期間が過ぎるたびに、ちょっとだけお酒を口にする。
翌日も少し飲む。気づけばビールを再開する。
そんなことを何度も繰り返してきました。
たぶん、死ぬまで飲まないというのは、私にはできないと悟っています。
だって、好きだから。
だからこそ、「うまく付き合う」しかない。
距離を保ちながら、共存していく。
そのバランスをどう取るかが、ここ数年ずっと私のテーマになっています。
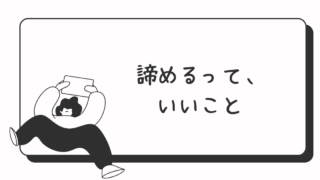
ノンアルという助け舟
そこで出てくるのが「ノンアル」や「炭酸水」。
最初は正直、気休め程度のつもりで手に取っていました。
でもこれが、意外と悪くない。
冷えたノンアルビールをグラスに注ぐと、見た目も香りもそこそこ“本物”。
炭酸が喉を刺激して、「あ、飲んでる感」もちゃんとある。
つまり、“儀式としての一杯目”をちゃんと置き換えてくれるんです。
「お疲れ、自分」って言いながらグラスを傾ける。
たとえ中身がアルコールじゃなくても、心のリセットにはなる。
嘘みたいですが、これが意外と大きい。
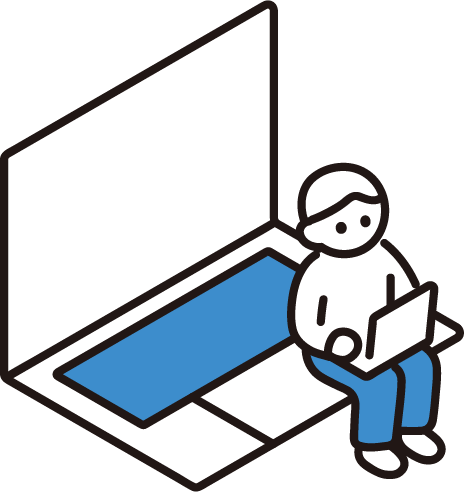
好きなノンアルは「グリーンズフリー」です。
好きな炭酸水は「ウィルキンソン タンサン」です。
最大の敵は「一杯目」
私の場合、一番危険なのは“最初の一杯”。
一杯飲むと、もう止まらない。
「せっかくだからもう少し」「ここまできたら今日はいいか」となる。
そして翌朝、後悔。
このパターンを何度も繰り返してきました。
だから大切なのは、「最初の一杯をいかに回避するか」。
ここが勝負どころです。
「飲むな」ではなく「飲んでもいいよ」
とはいえ、単純に「飲まないぞ!」と決意しても、たいてい失敗します。
人は「禁止」されると、余計に欲しくなる。
避けようとすればするほど、頭の中はお酒のことでいっぱいになる。
だから私は、考え方を変えました。
「飲んでもいい。でも、飲まない方がいいかもね?」
この“ゆるい自問”が、自分にはしっくりきたんです。
禁止ではなく、選択。
強制ではなく、納得。
たとえるなら、
「今日は飲んでもいいけど、ノンアルも美味しいじゃん?」
そんなふうに、自分に優しく問いかける。
この「許しながら、最適化へ導く」感じが、今の自分に合っている気がします。
飲むより先に満腹になる
もう一つ加えるなら、「空腹時に飲みたくなる」という性質があります。
なので手っ取り早くその感情を治めるのなら、空腹の逆になればいい。
つまり“満腹”になればいいのです。
だから私は、先ほどの優しい問いかけと併せて、“ご飯をもりもり食べる”ということも行います。
…なんだか書いていてすごくアホらしいですが、私にとってはこれがかなり効果的なのです。
しかも、アルコールが体に入っていないので、味覚や思考が敏感です。
だから、ご飯がいつもより美味しく感じられます。
色々と断酒にもメリットがあるのです。
行ったり来たりのリズム
先に書いた通り、実際のところ私は「飲む時期」と「飲まない時期」を行ったり来たりしています。
完璧な断酒でもなく、毎晩の晩酌でもない。
飲む時期には楽しみ、飲まない時期には身体の軽さを味わう。
面白いもので、数日間お酒を抜くと、頭が冴えてくるんです。
朝の目覚めも早く、仕事もはかどる。
そして、思考が深くなる。
たとえば読書をしても、内容がスッと入ってくる。
感性がクリアになる感じ。
逆に、しばらく飲み続けると、それがどんよりと曇っていく。
「あぁ、そろそろ抜いた方がいいな」と身体が教えてくれる。
そのサインを見逃さないようにしています。
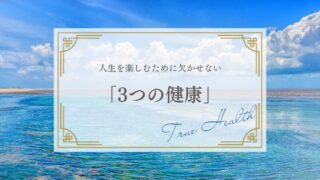
「ちょうどいい距離」は人それぞれ
結局のところ、お酒との付き合い方に正解はないと思うんです。
ゼロが合う人もいれば、週末だけがちょうどいい人もいる。
グラス一杯で満足できる人もいれば、仲間と飲んでこそ楽しい人もいる。
大事なのは、「自分にとって心地いいバランス」を見つけること。
お酒は悪ではないし、逃げでもない。
でも、“逃げるための道具”になってしまうと危うい。
その一線を、どこに引くか。
私の場合は、「自分の明日を奪わない飲み方」
これを意識しています。
明日も元気で、機嫌よくいたい。
そのためなら、今日の一杯をノンアルに置き換えるのも悪くない。
そんなふうに、少しずつ “飲まない選択”に愛着 が湧いてきました。
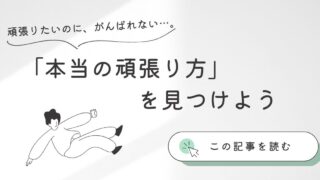
結論:お酒を敵にしない
お酒を「敵」として扱うと、心が窮屈 になる。
でも「友」として付き合えば、学び もある。
飲む日も、飲まない日も、自分のコンディションを感じながら過ごす。
それが、私にとっての「うまく付き合う」ということ。
今日も夜になれば、たぶん少し飲みたくなる。
そんな時は、自分にこう問いかけるんです。
「飲んでもいいよ。でも、ノンアルも美味しいじゃん?」
その一言で、なんとなく穏やかに1日を終えられる。
そんなふうに、自分とお酒の距離を調整しながら、
これからも“ちょうどいい関係”を探していきたいと思っています。
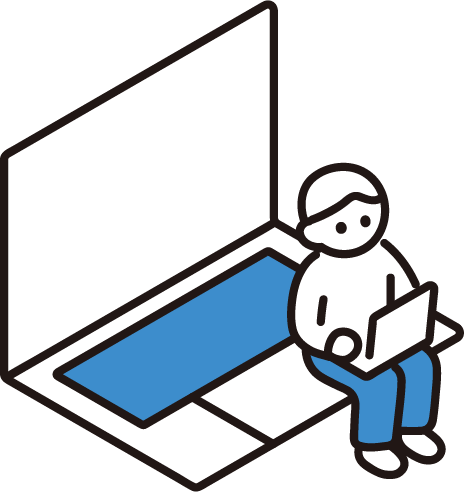
実は3年前に出会った本が、今回の私の断酒トライのキッカケになっているのです。
お酒で悩んでいる人は一読の価値ありです。
参考文献:
『Shall we 断酒?
ダンスを踊るように、楽しみながらお酒をやめませんか』
若林 毅(風詠社)